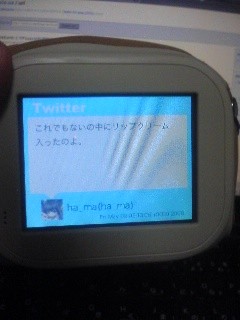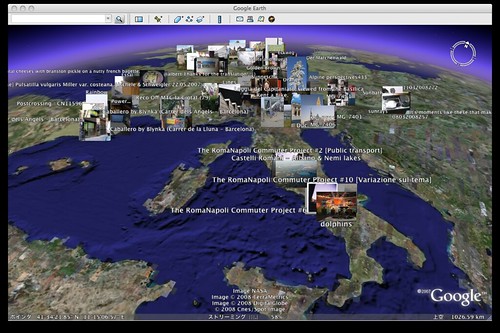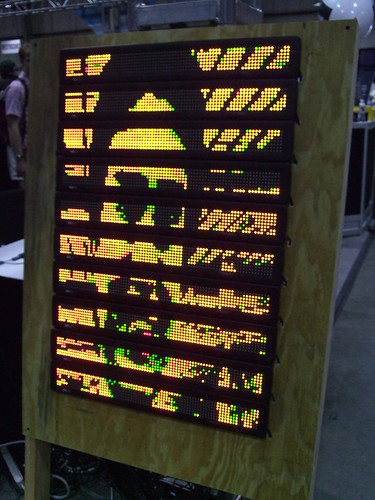chumbyは日本語フォントが入っていないので日本語が表示できないが、Flashの中のダイナミックテキストそのものにフォントを埋め込めば日本語が出せる。
ちょうどIMのAPIが動いてなかったので、twitterのfriends timelineを表示するchumby widgetを作ってみた。ただしフォントデータそのものを埋め込んで配布するのはライセンス的にまずそうなので、flaファイルのみの公開になります。自分の環境でコンパイルしてくださいIPAフォントを埋め込んで、swfも公開しました
ダウンロード → SourceCode (Flash CS3 / AS2)
(AS2が久しぶりすぎてやばかった)
ただしこの方法だとファイルサイズが100kb(chumby widgetの容量制限)を超えるので、USBから起動するしかない。
→ s.h.log chumbyで自作widgetをUSBメモリから起動する
■profile.xml
profile.xmlのusernumの数値を、自分のtimeline用に書き換える。これはtwitter上でのID。
twitter.com/homeで、自分のRSSフィードを見ると 123456.atom みたいな感じになっているので、その数値に書き換える。
intervalの秒数だけ、次の記事を読むまでwaitがかかる。デフォルトは8秒。
■Twitter APIをAS2で読む
XPath4AS2でxml版のフィードを読んだ。
FlashでBasic認証を通る方法がわからなかったので、protectをかけているユーザのtimelineは読めないかも知れない。
前に作ったXPath4AS2テスターが役に立った。
- s.h.log Flash – XPath4AS2でXPathテスター
- s.h.log FlashでFlickr REST-APIを呼ぶ
- trick7.com blog: xfactorstudioのXPath4AS2の使い方
■favorite
どうしてもふぁぼりたかったんだけど、FlashからBasic認証を通る事ができなくて無理だった。
http://user:pass@twitter.comの方法も、Base64エンコードしてLoadVarsにaddRequestHeaderするのも、getURLも駄目。
ブラウザの中で動いているわけではないのでログイン済みのcookieを共有するも出来ない。
cgiでproxyすればいいんだけど。
■thumbnail
USBから起動した場合、サムネイルが読めない。
同じ画像ファイルでwebにアップした場合は読めたので、profile.xmlの記述ミスかも。
■setIntervalがおかしい
PC上で実行している時は問題ないんだけど、ChumbyのFlashLite3上でsetIntervalを使ってタイマ処理を行っている時、4秒以上待てない。10秒などを指定すると、4秒ぐらいでタイマ処理が回ってしまう。調べても特にFlashLiteは特別という記述は見あたらなかったので、なんだかわからないけど、さすがに4秒はchumbyから目を離せなくなってしまうので今回は1秒を数えるsetIntervalを作ってさらにカウントアップする変数を用意して、時間を数えるようにした。
■プログラム
全部twitter.flaの1フレーム目に書いた
importcom.xfactorstudio.xml.xpath.*;
if(!interval)interval=10;
if(!usernum)usernum=3631571;vartwitterXml:XML=newXML();
twitterXml.ignoreWhite=false;varxmlUrl=”http://twitter.com/statuses/friends_timeline/”+usernum+”.xml”;
twitterXml.onLoad=twitterXml_onLoad;
twitterXml.load(xmlUrl);varint_id;
functiontwitterXml_onLoad(success:Boolean){
if(success){
trace(“XMLloadsuccess!!”);
loading._visible=false;
preLoadIcon(twitterXml);
int_id=setInterval(count_sec,1000);
loadNextStat();
}
else{
trace(“XMLloaderror!!”);
}
}functionpreLoadIcon(stats:XML){
//trace(stats);
varicons:Array=XPath.selectNodes(stats,”statuses/status/user/profile_image_url/text()”);
trace(icons.length);
for(vari:Number=0;i<icons.length;i++){
varloader=newmx.controls.Loader();
loader.contentPath=icons[i];
//loader.load();
//trace(loader.autoLoad);
trace(loader.contentPath);
}
}varstat_id=0;
varfav=”false”;
functionloadStats(stats:XML,num:Number){
varlen=XPath.selectNodes(stats,”statuses/status”).length;
if(num>len){
clearInterval(int_id);
loading._visible=true;
twitterXml.load(xmlUrl);
n=1;
return;
}
varupdate=XPath.selectNodes(stats,”statuses/status[“+num+”]/text/text()”);
fav=XPath.selectNodes(stats,”statuses/status[“+num+”]/favorited/text()”);
variconUrl=XPath.selectNodes(stats,”statuses/status[“+num+”]/user/profile_image_url/text()”);
varuserName=XPath.selectNodes(stats,”statuses/status[“+num+”]/user/name/text()”);
varscreenName=XPath.selectNodes(stats,”statuses/status[“+num+”]/user/screen_name/text()”);
vardate=XPath.selectNodes(stats,”statuses/status[“+num+”]/created_at/text()”);
stat_id=XPath.selectNodes(stats,”statuses/status[“+num+”]/id/text()”);
iconLoader.contentPath=iconUrl;
//favStar.gotoAndStop(fav);//labelで移動
labelUpdate.text=update;
labelUserName.text=userName+”(“+screenName+”)”;
labelDate.text=date;
trace(fav);
}varsec=0;
functioncount_sec(){
sec++;
if(sec>=interval){
sec=0;
loadNextStat();
}
}varn=1;
functionloadNextStat(){
trace(“loadNextStat”);
loadStats(twitterXml,n++);
}