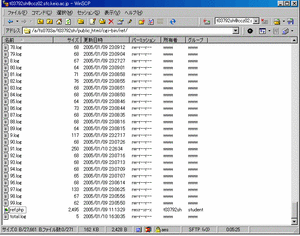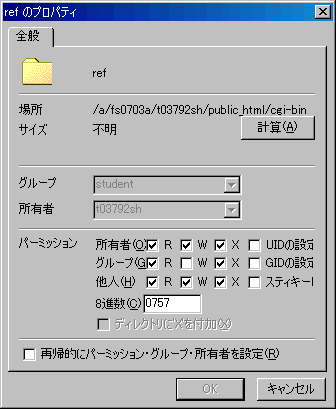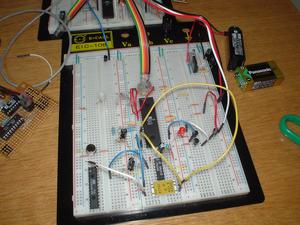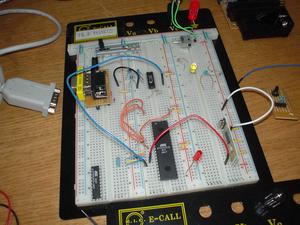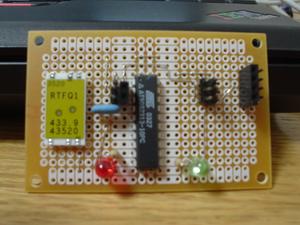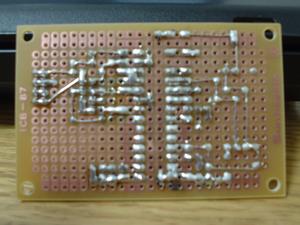出かける前に昨日作った奴にアクセスカウンタを付けた
http://shokai.org/archive/php/ref0.20.zip
インデックスページ用
>>
<<
のように、引数にshowcountT=1を渡すとhttp://web.sfc.keio.ac.jp/~shokai/ の右側のように、全体のアクセス数を表示する。(数字だけ表示される)
リファラーは、一番最近のエントリーに保存する事にした。
個別エントリーページの方は
>>
<<
に変わった。引数にshowlist=1を渡すと、そのエントリのリファ一覧を表示する。
引数にshowlistもshowcountT書かなければ(もしくは0を与えれば)何も表示しなくなる。
*変更点
-引数showlist, showcountT オプションを付けた
-phpスクリプト内 3行目 $countT_init = 0; でカウンタの初期値を設定可能
*今後(メモ)
-リファ一覧のRSSを吐く → Flash等と連携可能。色んなblogがアクセス元を標準化&公開するようになると面白い。以前のはてなアンテナを巡回する奴とか
-エントリ毎のアクセス数も記録
-アクセスの多いエントリ上位n件を表示
-検索ワードをgoogle以外にも対応
-自サイト内の移動をなんか頭良い形で見せる
-エントリ毎じゃなく、日毎にアーカイブを作成してる人も使えるようにする
とか
*追記
-個別エントリー用のjavascriptの、cgiへのパスが間違ってたので修正
*このblogのディレクトリ構造
-public_html
–index.html
–cgi-bin
—ref
—-ref.php
–archives
—year
—-manth
—–hogehoge.html(個別エントリ)
相対パス指定の参考に。相対パスは ../ で一つ登る。
hogehoge.htmlからref.phpへのパスは、 ../../../cgi-bin/ref/ref.php になる。